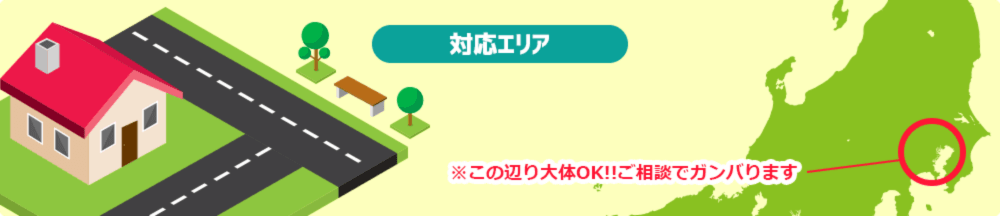スプレー缶は、正しい方法で処分しないと事故やトラブルの原因になることがあります。本記事では、基本の処分手順から注意点、不用品回収業者へ依頼する方法までをわかりやすく解説します。安心して処分できるよう、ぜひ参考にしてください。

【まず記事を読む前に】不用品回収くまのての料金プランは、業界最安値の料金設定で、不要になった物が多ければ多いほどお得になる定額プランを提供いたしております。
「スプレー缶を捨てたいけど、どの業者に頼めばいいかわからない」「他にもテレビや大量の不要品を処分したい」とお悩みの場合は是非お問い合わせ下さい!
スプレー缶の捨て方は?基本となる3つの手順を紹介

スプレー缶は、ガスが充填されているため、一般のごみとは違った処分手順が必要です。以下の3つの基本ステップに沿えば、安全に処分できます。
- ・中身を処分する
- ・透明な袋へ入れる
- ・自治体が指定する日・場所に捨てる
中身を処分する

1つ目の手順は、中身を完全に使い切ることです。火気のないところを選びましょう。
使い切れない場合は、専用のガス抜きキャップを使ってガスをしっかり抜きましょう。ガス抜きキャップはホームセンターやネットで購入可能です。
作業の際は、手袋や保護メガネを着けて安全対策を忘れないことが大切です。ガス抜きの際、噴射音が大きくなることがありますが、問題ありません。
また、万が一ガスが漏れている場合は、すぐに作業を中止し、換気を行いましょう。この手順を確実に守ることで、火災や爆発のリスクを大幅に減少させることができます。
透明な袋へ入れる

次に透明な袋に入れる必要があります。透明な袋に入れるのは、回収作業員が中身を確認しやすくするためです。
中身が見えないと誤って一般ごみと処理され、火災などの危険につながる可能性があります。透明な袋に入れる際は、完全に冷えていることを確認してください。
また、袋に入れる前に、缶に残ったガスや液体が漏れないようにチェックすることも重要です。袋に入れた後は、口をしっかりと閉じて、収集日に備えましょう。
この手順を守ることで、安全かつ適切に処分できるようになります。
自治体が指定する日・場所に捨てる
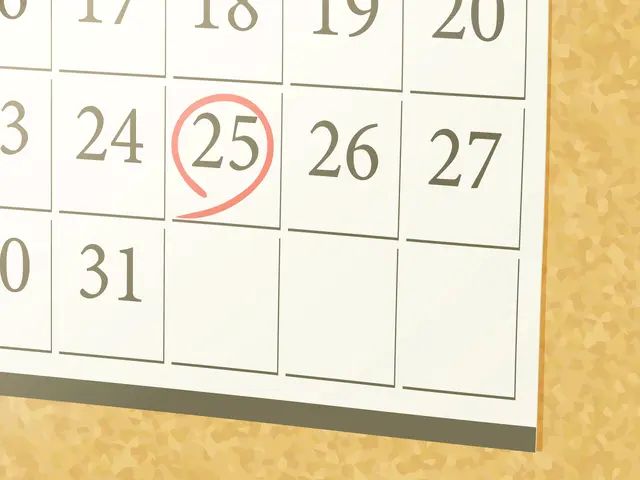
スプレー缶を正しく処分するための手順は、自治体が指定する日・場所に捨てることです。各自治体は特定の日にスプレー缶や危険物の回収を行っているため、そのスケジュールを確認することが重要です。
回収日は、自治体のホームページやごみカレンダーで確認できます。持ち込むときは透明な袋に入れ、口をしっかり閉じて、ほかのごみと混ぜないようにしましょう。
回収場所は通常、指定されたごみステーションや一時的な回収ポイントとなります。万が一、回収日を逃した場合は、次の回収日まで自宅で保管するか、適切な処分施設に持ち込むことを検討してください。
自治体のルールを守れば、安全に処分でき、環境への負担も少なくできます。
スプレー缶を出す前に必ず確認したい注意点(火災事故防止)

スプレー缶は、捨て方を間違えると収集車や処理施設で火災につながる恐れがあります。また、適切な道具を使うことも欠かせません。特に室内で複数の缶を処理すると、わずかな火種で爆発につながる危険があるため、絶対に避けましょう。まずは次のポイントを守って、安全に処分してください。
近年では「穴あけを推奨しない」自治体も増えています。理由は、作業自体に危険があるからです。残留ガスがあると爆発や火災のリスクが高まります。そのため、最終的には自治体の指示に従うことが何よりも大切です。
- ・中身は必ず使い切る(火気のない屋外・風通しの良い場所で行う)
- ・穴あけはしない(危険なためNGとしている自治体が多い)
- ・透明/半透明の袋に「スプレー缶だけ」をまとめて入れ、燃やすごみ等とは分けて出す
- ・プラスチック製キャップ等は、自治体ルールに従って別分別する
- ・中身が抜けない・大量に残っている場合は、無理に処理せず自治体・メーカーへ相談する
ルール(収集日・分別区分・袋の出し方)は自治体で異なります。以下は自治体の公式案内と、中身を安全に抜く方法の専門団体の公式案内です。
※上記は代表例です。お住まいの自治体の「スプレー缶(エアゾール缶)」の出し方を必ず確認してください。
必ず自治体のホームページやごみ処理ガイドラインを確認してください。
スプレー缶の中身を空にする方法

スプレー缶の中身を確実に空にするには、次の3つの方法があります。
- ・空気中に噴射する
- ・新聞紙に染み込ませる
- ・空になっているかをチェックする
順番に見ていきましょう。
空気中に噴射する
殺虫剤など、空気中に出しても問題ないものは、屋外でボタンを押し続けて噴射します。ただし中身が多く残っている場合は、環境や健康に影響を与える可能性があるため、数回に分けて行いましょう。
新聞紙に染み込ませる
カラースプレーや整髪料など、飛び散ると困るものは新聞紙に吹きつけて染み込ませます。その際は新聞紙をビニール袋に入れて、周囲に飛び散らないよう注意しましょう。
使い切った後の新聞紙は、燃えるゴミとして処分できます。
空になっているかをチェックする
中身が空かどうかは、缶を上下に振って確認できます。「シャカシャカ」と音がしなければ、空になっているサインです。
確認後は、自治体のルールに従って処分しましょう。
スプレー缶の捨て方で注意すべき点とは?

スプレー缶を捨てるときには、守るべき注意点があります。ここでは特に重要なポイントを整理して解説します。
正しく分別して捨てる
まずは中身を完全に使い切り、ガスをしっかり抜くことが大切です。そのうえで、自治体のルールに従って正しく分別しましょう。
多くの自治体では、金属資源ごみや有害ごみに分類されます。他のごみと混ぜると火災や爆発の原因になるため、必ず指定の方法で処分してください。
分別ルールは地域ごとに異なるため、必ず事前に確認しましょう。
各地域の処分ルールを理解しておく
処分ルールは地域ごとに異なります。正しい方法を知るには、自治体のごみ処理ガイドや公式サイトを確認することが欠かせません。
多くの自治体は、スプレー缶を資源ごみや有害ごみとして扱い、決められた日に収集しています。地域によっては、専用の回収ボックスを設置している場合もあります。
ルールを守って処分すれば、安全性を確保できるだけでなく、環境保護にもつながります。
スプレー缶の捨て方には無料と有料の2通りある

スプレー缶の捨て方には、大きく分けて「無料」と「有料」の2通りがあります。ここでは、自治体に回収してもらう方法と、不用品回収業者に依頼する方法をわかりやすく解説します。
自治体で無料回収してもらう
自治体で回収してもらう場合、費用はかかりません。基本的には普段のゴミ出しと同じ流れで処分できます。
ただし、スプレー缶の出し方は自治体ごとに細かいルールがあります。ルールを守らないと回収してもらえないこともあるので注意が必要です。
中身をしっかり処分したうえで、指定の日時・場所を守って出しましょう。
有料で業者に回収してもらう
もう一つの方法は、民間の不用品回収業者に依頼することです。家具や家電の回収イメージが強いですが、スプレー缶を受け付けている業者もあります。
ただし、スプレー缶は危険物にあたるため、すべての業者が対応しているわけではありません。依頼前に必ず確認しましょう。
業者を利用する場合は費用がかかります。ただし、家の不用品をまとめて片付けたいときや、スプレー缶が大量に残っているときには便利です。
なお、不用品回収業者は各地で多く存在しますが、なかには違法な営業をしている業者もあるため注意が必要です。利用前には、許可証の有無などを確認し、安心して依頼できる業者を選びましょう。
不用品回収業者へ依頼するメリット

不用品回収業者に依頼すると、自分で処分するよりも安全で便利に片付けられます。ここでは主なメリットをわかりやすく解説します。
穴をあけなくてよい
不用品回収業者に依頼すれば、危険な「穴あけ作業」をする必要がありません。自分で行うとガス漏れや爆発のリスクがありますが、専門業者に任せれば安全に処分できます。
特に不安がある場合や大量に処分したいときに便利です。
中身を空っぽにしなくてよい
不用品回収業者に依頼すれば、中身を完全に使い切る必要はありません。使用期限切れや残量がある缶でもそのまま処分してもらえます。
手間を省けるうえ、安心して任せられるのが大きなメリットです。
他の不用品があればあわせて回収してもらえる
不用品回収業者は、スプレー缶以外の不用品もまとめて引き取ってくれます。家具や家電、小型家電まで一度に処分できるため効率的です。
特に引っ越しや大掃除では、時間と手間を大幅に削減できます。さらに業者は適切な処分方法を知っているので、環境面でも安心です。
不用品回収「くまのて」を利用されたお客様の声

不用品の回収をお願いしたく、くまのてさんにお願いしました。
1回目も2回目もオペレーターさんや、作業員の印象が良かったので、再度利用しました!
当日、荷物が追加で増えてしまっても、その場で計測してくれて引き取ってもらえるのが凄く良かったです。
丁寧に搬出作業を行ってくれますし、細かいゴミなども「これは回収しますか?」と聞いてくれるので、凄くありがたいです。
また、利用したいと思います!

まとめ

スプレー缶は通常のゴミとは処分方法が異なり、誤った扱いをすると爆発の危険があります。必ず「危険物を扱っている」という意識を持ち、正しい方法で処分しましょう。
一般的には自治体のルールに従って回収してもらうのが基本です。一方で、不用品回収業者に依頼すれば有料にはなりますが、中身を出し切ったり穴を開けたりする手間が省けるため、安全かつ手軽に処分できます。
さらに、大型の家具や家電の処分とあわせてスプレー缶をまとめて引き取ってもらうことも可能です。処分するものが多い場合は、不用品回収業者へ相談するのも有効な方法です。
よくある質問FAQ
- スプレー缶は穴あけが必要ですか?
- 穴あけは不要(または非推奨)としている自治体が増えています。穴あけはケガや引火のリスクがあるため、中身を使い切ったうえで、自治体のルールに従って出すのが基本です。
- スプレー缶の中身が残っていても捨てられますか?
- 原則として、中身は使い切ってから出します。残ったまま出すと、収集車や処理施設で火災につながる恐れがあります。使い切れない場合は、無理に処理せず自治体やメーカーの案内を確認してください。
- ガス抜きキャップは使った方がいいですか?
- ガス抜きキャップが付いている製品は、取扱説明に従って使用すると安全に中身を出し切りやすくなります。必ず火気のない屋外など風通しの良い場所で行い、自治体の指示に従って処分してください。
- スプレー缶の中身を安全に抜くにはどこで作業すればいいですか?
- 火気のない屋外で、風通しの良い場所で行うのが基本です。室内や火気の近くで作業すると引火の危険があります。自治体や専門団体の手順を確認しながら行ってください。
- 錆びたスプレー缶や古いスプレー缶も同じ捨て方でいいですか?
- 基本は同じですが、錆びや腐食が進んでいる場合は漏れや破裂のリスクがあるため注意が必要です。中身を安全に使い切れない場合は、自治体の相談窓口やメーカー案内に従って処分してください。
- スプレー缶は「燃やすごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」のどれですか?
- 自治体によって分類が異なります。多くは「資源」や「危険ごみ」など専用区分で回収されますが、不燃ごみとして扱う地域もあります。必ずお住まいの自治体の分別ルールを確認してください。
- スプレー缶は袋を分けて出す必要がありますか?
- 分けて出すよう求める自治体が多いです。透明または半透明の袋にスプレー缶だけを入れ、燃やすごみ等と混ぜずに出してください。出し方(表示の有無など)は自治体ルールに従います。
- キャップ(プラスチック部分)は缶と一緒に出していいですか?
- 自治体によって異なります。多くはプラスチックごみとして別分別します。缶と一緒に出してよい地域もあるため、自治体の分別ルールに従ってください。
不用品回収くまのての料金プランは、業界最安値の料金設定で、不要になった物が多ければ多いほどお得になる定額プランを提供いたしております。
さらに、買取できる物があった場合、表示価格から更にお値引になります!
古物商許可:東京公安委員会 第308781904820号